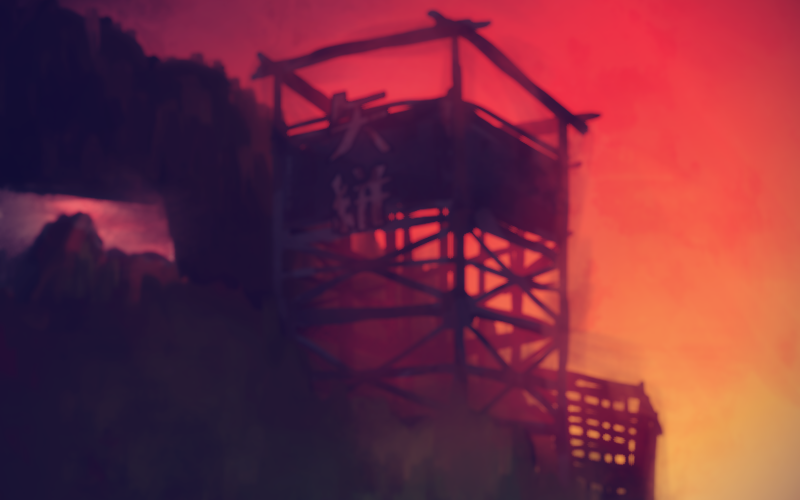※未投稿ネタ・セルフ二次創作
モブキャラ視点の短編。
炭鉱町とカメラマン
「いいかい××君、もしもあの鉱山で君の身に何かが起こっても、僕たちは一切その責任を負うことが出来ないんだ。」
「……君がどうしてもと言うなら僕が付き添う。けれど今日は午後から用事があってね。どうか日を改めて欲しいんだ。」
──そんな市長との約束を、私はついに守ることができなかった。
私は今、重たいカメラを抱え、生い茂る雑草を掻き分けて、たった一人炭鉱の跡地へ足を踏み入れようとしている。
もはや道と呼べない草むらをしばらく進んでいると、ようやく視界が開け、そこには先日雑誌で見たものと全く変わらぬ光景が広がっていた。
流れ落ちる汗を拭うことも忘れて、素早くカメラを構える。
かつて石炭の採掘で栄えていたというチトセヤガスリの炭鉱町は、確かに存在していたのだ!
人の消えた廃墟群の中で聞こえてくるのは、蝉たちの甲高い鳴き声と、興奮冷めやらぬ私のくだらない独り言。
炭坑で働く人々が毎日掲げていたのであろう安全標語の看板や、マニアの間では有名だった巨大な櫓。
取り付けられている「矢絣炭鉱」のパネルは錆びて劣化し、今にも崩れてしまいそうだ。
ボロボロの建物を見ていると、市長があれだけ危険、危険とうるさく言っていたのも頷ける。
だからこそ私は早いうちにこの廃墟を目にしたかった。
写真という形で、一枚でも多くこの炭鉱町の記憶を後世に残さねばならないと思ったのだ。
廃屋内のレイアウトを極力崩してしまわないように慎重に足を踏み入れ、静かにシャッターを切る。
立て付けが悪く半開きの窓やドアから雨風に曝された影響で残留物は床に散乱しているが、当時の生活の様子は部外者の私でも鮮明に浮かぶ。
それほど綺麗に、この町は人だけが消えていた。
◇◇◇
炭坑すらまだ辿り着けていないのに、この地を訪れてからすでに数時間経過している。
何百枚と写真を撮ってもキリがない素晴らしい廃墟群。
低いブロック塀に腰を掛け、カメラ内のデータを整理しながら考える。
結局無許可で立ち入ったため、上にバレてしまうと厄介だ。
そろそろ下山するべきか──── ふと一つの考えが脳裏を過る。
この地域の夕焼けに照らされた炭鉱町はさぞかし美しいのだろう。
あらゆる雑誌を読み漁っても、この時間帯以降の写真は見当たらない。
日没後の山は非常に危険なのだが、せっかくここまで来たのだ。
私はどうしても夕焼けと廃墟群をこのカメラに収めたくてたまらくなった。
欲張らず、撮ったらすぐに帰るとしよう。 いよいよ日が落ち始めた。
夕焼けの茜色に染まった炭鉱町は思った通り、いやむしろ、想像以上の美しさだった。
過去の住民たちも、仕事終わりには決まってこの空を見ていたに違いない。
しかし、あの時代にはもう二度と、誰一人として戻ることは出来ないのだ。
時の流れの残酷さに、部外者ながら心を揺さぶられる。
たった一枚撮るだけでカメラを持つ手も止まってしまうほど、私はその茜色に魅入っていた。
あまりの美しさにため息が漏れる。 早く帰らなくてはいけないという焦燥感も、いつの間にか忘れてしまっていた。
◇◇◇
「こら!こんな所で何をしているんだ?」
背後で突如聞こえた私以外の人物の声に、思わず心臓が飛び出しそうになった。
「す、すみません!どうしても撮りたくって……」
慌てて弁明し、頭を下げる。
そこに立っていたのは壮年の男性で、市長と似た帽子を被っていた。おそらく見回りに来た役所の人だろう。
「若い子はこれだから困ったもんだ……ほら、帰るよ」
男性は片手にランタンを握っている。辺りはすっかり真っ暗になっていたが当然廃墟の街灯は灯らない。
もしもこの人に出会わなかったら今頃立派な迷子だ。自分が情けなくなって、涙が溢れる。
「ちゃんと送ってやるから泣かないの!」
「……すみません」
前を歩く男性の後ろを、トボトボついて行く。
役所の人に見つかった時点で後でこっぴどく叱られることは明白で、自業自得とはいえ胃がキリキリと痛む。
「いい写真は撮れたかい。」
話を切り出したのは向こうからだ。
その声は意外にも穏やかだったが、私は一言「はい。」と返答するので精一杯だった。
「それは良かった。アレでも昔はいい町だったからね。」
「次があったらお友達と来なさい。一人じゃ心細いでしょ」
彼は怒った顔を全く見せない。
一言、二言と他愛のない会話をしながら進んでいくうちに街の灯りが見えてきた。
街灯の下には見覚えのあるシルエットがひとつ。
……今朝に話した市長だ。
思わず「あっ!」と声が出る。
その険しい顔から、自分はとんでもないことをしてしまったと改めて痛感した。
「あれほど危険だって言っただろう!どうして言うことを聞かなかったんだ!」
朝の優しげな声は何処へやら、初めて聞く怒号に身を竦ませる。父親に怒られる子供のそれと同じ光景だ。
思い返すと恥ずかしくなるほど、ぼろぼろ泣きながら市長に謝る。
勝手に山を登り、炭鉱町に行ったこと。日が暮れても帰ろうとしなかったこと。
「とにかく、君が無事に下山出来て良かったけどね」
「いいえ、見回りの人に会わなかったら、今頃どうなっていたか……」
すると市長は怪訝な顔をする。
「……人に、会ったの?」
「あの男の人ですよ、ほら───」
そこに、さっきまで私を案内してくれていた男性は居なかった。
周囲を見回しても、山の中では眩しいくらいだったランタンの灯さえ何処にも見当たらない。
「……あれ?」
その場にぽかんと立ち尽くす私と市長の間を、真夏の生ぬるい風が吹き抜けていった。
◇◇◇
「───この前、こんな子がいてさ。本当に男の人が居た、一緒に下山したんだって聞かないんだよ」
「……どうせ親父に会ったんだろ。お節介なところがよく似てるよ」